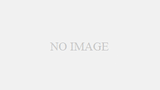これまで「自分が生徒」の立場で塾に通う立場だった方も多いですよね。でも、これからは「自分が先生」です。「通ってくる生徒」と「講師」とでは関係の作り方は少し異なります。この記事で整理して、それぞれとの接し方について考えてみましょう。
教室長との関係
講師にとって、教室長は上司です。通う生徒からは、教室長の運営の仕方によって様々ですが、「頼れるベテラン先生」であることが多いです。もしくは、「ちょっと小うるさい人」なんてことも。
しかし、講師になると、雇用主であったり、上司であったり、「上の立場」の存在です。どんなにフレンドリーに接してくれる教室長であっても、対応する時は必ず「上司」の線引きをしましょう。
多くの大手企業など多数教室展開のある学習塾の教室長は、「本社/本部」と「教室現場」の足がかり的な存在。もっと言うと中間管理職のようなもの。教室にはその教室長の運営方針が大きく色として出る場でもありますが、「このルールがあるよ!」と本部や本社から言われる立場でもあります。
教室長とのいい関係を作るためには、「指示をきちんと聞く、実行する」「生徒や同僚講師といい関係を築く」ことが大切です。きっとあなた自身の指導のしかたや、生徒との接し方もあるでしょう。しかし、教室長からの指示を聞いてきちんと実践して動いてくれる、というのは、教室長が求めていることです。ルールや指示の動き方の中で自分自身の色を出していけるといいですね。
生徒との関係
先生になる、ということは生徒は顧客になります。これまで生徒としてサービスを受けてきていたみなさんも、これからは生徒ではありません。教室に所属する講師にとって、生徒や保護者からの評価は重要です。「同じサービスを受ける仲間」から、サービスを提供する相手にかわります。
生徒への指導や対応の先には保護者がいることを忘れてはいけません。教室や教室長、会社にとっての顧客は保護者です(契約的な面で)。そのため、保護者からのクレームや生徒からのクレームは命取りになることも。ひとつひとつの言動に注意を払わなければなりません(が、媚びへつらう必要はありません)。いい授業の提供、いい先生としての言動を心がけましょう。
保護者との関係
ほとんどの学習塾では、直接保護者と講師が関わる場面は少ないです。むしろ、ゼロと言ってもいいくらい。ですが、先述の通り、生徒の先に保護者がいます。生徒と保護者の間の家庭での会話を中心に講師の口コミが伝わります(それがどんなものであっても)。そこから、保護者が教室に送迎で来た時や、面談時に教室で見た様子から、講師の評価が決まります。教室にいる間(勤務中)の態度には気を配りましょう。
他の講師との関係
他の講師との関係は教室によってかなり変わります。教室長や、講師内のリーダーなどがどのような方針かにもよります。が、「敵」を作らないに越したことはありません。初出勤時や初対面では特にその後の関係を左右することになります。しっかり挨拶をしておきましょう。
教室によっては、ベテラン講師が講師育成に入ることもあります。教室長ではないから、と油断しないようにしましょう。育成の担当者は教室長と連携しています。
まとめ
誰に対しても「敵」を作らないこと